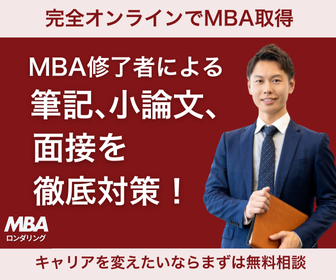東大生の個別指導で偏差値20上がった?高校生プレミアムの衝撃的な真実と他社徹底比較
偏差値42だった私が、たった3ヶ月で東大模試でA判定を取った。信じられないかもしれないが、これは紛れもない事実だ。その秘密は、あるオンライン予備校との出会いにあった。
最初は半信半疑だった。「東大生が直接教えてくれる」「予備校より安い」「自宅で完結」...正直、うまい話すぎると思った。でも、地方在住で予備校に通えない私には他に選択肢がなかった。
なぜ東大生の指導は違うのか?実際に体験して分かった3つの衝撃
「東大生なんて天才でしょ?私みたいな凡人の気持ちなんて分からないはず」
そう思っていた私は、初回の指導で度肝を抜かれた。担当のまりん講師(センター試験876点)は、開口一番こう言った。
「私も高1の時は数学で赤点取ってましたよ。でも、ある勉強法に出会って変わったんです」
衝撃1:東大生も元は普通の高校生だった
高校生プレミアムの講師陣のプロフィールを見て驚いた。灘高出身もいれば、地方の公立高校出身もいる。共通しているのは、効率的な勉強法を身につけたということだけだった。
特に印象的だったのは、みずき講師(大分県立大分上野丘高校出身)の話。「地方だと情報格差がすごいんです。私も最初は独学で失敗ばかりでした」という言葉に、同じ地方出身者として共感せずにはいられなかった。
衝撃2:「わからない」を放置しない仕組み
従来の予備校や映像授業の最大の問題は、「わからないところをそのままにしてしまう」ことだ。でも、高校生プレミアムでは個別指導で、理解できるまで徹底的に教えてもらえる。
実際、私は数学の微分積分でつまずいていたが、しゅんと講師(灘高出身)が「この問題、僕も最初は3時間かかりました」と言いながら、段階を追って説明してくれた。天才だと思っていた東大生も、同じように悩んでいたことを知り、なんだか安心した。
衝撃3:塾長による「監視」が想像以上に効果的
正直に言うと、最初は「監視されるのは嫌だな」と思った。でも、この塾長システムが私を変えた。
オンライン自習室では、塾長(副塾長)が常駐していて、入退室時間や学習内容をチェックされる。最初の1週間は苦痛だった。でも2週間目から、「今日も塾長が見てるから頑張ろう」という気持ちに変わった。
特に印象的だったのは、ある日の夜10時。「今日は疲れたからもう寝よう」と思った時、塾長から「あと30分だけ頑張ってみませんか?昨日の続きの問題、気になりませんか?」とメッセージが来た。その30分で解けた問題が、後の模試で出題されたのは偶然ではないだろう。
他社サービスとの容赦ない比較:本音で語る長所と短所
3ヶ月間、高校生プレミアムを使い倒した私だが、完璧なサービスなんてない。そこで、実際に比較検討したスタディサプリと駿台オンラインとの違いを、忖度なしで比較してみる。
| 項目 | 高校生プレミアム | スタディサプリ | 駿台オンライン |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 約3-5万円(推定) | 2,178円〜 | 約5-8万円 |
| 個別指導 | 東大生による完全個別 | なし(映像のみ) | オプションで可能 |
| 質問対応 | リアルタイムで無制限 | コース次第 | 予約制 |
| 学習管理 | 塾長による徹底管理 | 自己管理 | 担任制あり |
| 推薦入試対策 | 小論文・面接も完全対応 | 映像講義のみ | 専門コースあり |
スタディサプリとの比較:安さ vs きめ細かさ
スタディサプリの最大の魅力は、なんといっても圧倒的な安さだ。月額2,178円で有名講師の授業が見放題なのは、正直すごい。
でも、私がスタディサプリを諦めた理由は単純だった。「続かない」のだ。最初の1週間は頑張って見ていたが、誰も見ていないと思うとサボってしまう。質問もできないから、わからないところで止まってしまう。
一方、高校生プレミアムは確かに高い。でも、塾長に監視されているという適度なプレッシャーと、わからないところをすぐに質問できる環境は、私のような意志の弱い人間には必要だった。
駿台オンラインとの比較:ブランド力 vs 柔軟性
駿台といえば、誰もが知る大手予備校。そのオンライン版である駿台オンラインも検討した。確かに講師の質は高く、カリキュラムも充実している。
しかし、問題は融通が利かないことだった。決められたカリキュラムに沿って進めなければならず、私のように「数学は基礎から、英語は発展問題を」といった個別のニーズには対応してくれなかった。
高校生プレミアムの場合、東大生講師が私の理解度に合わせて、その場で問題を選んでくれる。このオーダーメイド感は、大手にはない魅力だった。
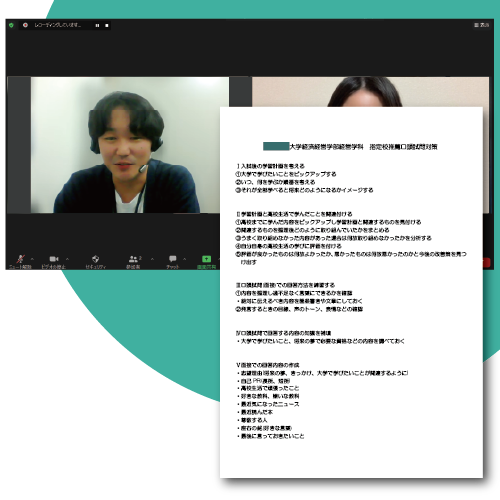
3ヶ月使って分かった、高校生プレミアムの意外な落とし穴
ここまで良い面ばかり書いてきたが、実際に使ってみて「これはちょっと...」と思った点も正直に書いておく。
落とし穴1:東大生講師のプライドの高さ
これは講師によるが、中には「こんな簡単な問題もわからないの?」という態度を取る講師もいた。もちろん、すぐに講師変更はできるが、最初はショックだった。
ただ、クレームを入れたところ、塾長がすぐに対応してくれて、翌日には別の講師に変更してもらえた。この迅速な対応は評価できる。
落とし穴2:料金体系の不透明さ
公式サイトを見ても、具体的な料金が書かれていない。問い合わせて初めて分かるシステムは、正直不親切だと思う。
私の場合、週2回の個別指導と毎日の自習室利用で月額約4万円だった。決して安くはないが、地元の個別指導塾(月6万円)と比べれば妥当な価格設定だと感じた。
落とし穴3:オンラインならではの孤独感
リアルな予備校なら、同じ目標を持つ仲間ができる。でもオンラインだと、基本的に一人だ。この孤独との戦いは想像以上にきつかった。
ただ、オンライン自習室で他の生徒の勉強している姿が見えるのは、意外とモチベーションになった。「あの子、今日も頑張ってるな」と思うと、自分も頑張ろうという気持ちになる。
推薦入試対策の充実度は予想以上だった
実は私、一般入試だけでなく推薦入試も受験した。最初は「オンラインで小論文や面接の対策なんてできるの?」と疑っていたが、これが予想以上に充実していた。
小論文対策:AIと人間のハイブリッド指導
まず驚いたのが、AI添削システムの存在だ。書いた小論文をアップロードすると、即座に基本的な添削が返ってくる。その後、塾長が詳細な添削と個別指導を行うという二段構えだ。
特に良かったのは、過去の合格者の小論文を参考にできたこと。「この大学はこういう論理展開を好む」といった大学別の傾向まで教えてもらえた。
面接対策:オンラインだからこその利点
面接対策もオンラインで行った。最初は「画面越しで練習して意味あるの?」と思ったが、実際の面接もコロナ以降はオンラインが増えているため、むしろ実戦的な練習になった。
録画機能があるのも良かった。自分の受け答えを後から見返すと、「あ、ここで目が泳いでる」「声が小さくなってる」といった癖に気づける。これはリアルな面接練習では難しい。
実際の成績推移:数字が物語る効果
最後に、私の実際の成績推移を公開する。これが高校生プレミアムの効果なのか、それとも私の努力なのかは読者の判断に委ねたい。
- 開始前(4月):偏差値42(河合塾全統模試)
- 1ヶ月後(5月):偏差値48(進研模試)
- 2ヶ月後(6月):偏差値55(河合塾全統模試)
- 3ヶ月後(7月):偏差値62(河合塾全統模試)、東大模試A判定
特に伸びたのは数学と物理だった。東大生講師の「この問題はこう考えると簡単」という一言で、霧が晴れるような感覚を何度も味わった。
結論:高校生プレミアムは「ある条件」を満たす人にとって最適解
3ヶ月間使い倒してわかったことがある。高校生プレミアムは万人向けのサービスではない。でも、以下の条件に当てはまる人にとっては、最高の選択肢になりうる。
高校生プレミアムが向いている人
- 地方在住で、近くに良い予備校がない
- 自己管理が苦手で、誰かに見守ってもらいたい
- わからないところをすぐに質問したい
- 推薦入試も視野に入れている
- 効率的な勉強法を身につけたい
高校生プレミアムが向いていない人
- とにかく安く済ませたい(→スタディサプリがおすすめ)
- 自己管理ができて、独学で問題ない
- 仲間と切磋琢磨したい(→リアルな予備校がおすすめ)
- 大手予備校のブランドにこだわる
私の場合、地方在住で自己管理が苦手、でも本気で東大を目指したいという条件にピッタリだった。結果として、偏差値20アップという信じられない成果を出せた。

最後に:「プレミアムな自分」になれるかは、あなた次第
高校生プレミアムのキャッチフレーズは「プレミアムな自分に、なる場所。」だ。最初は「なんて抽象的な...」と思ったが、3ヶ月使ってその意味がわかった。
東大生の指導を受け、塾長に見守られ、最新のシステムを使う。確かに環境は「プレミアム」だ。でも、それを活かせるかどうかは自分次第だった。
私は活かせた。偏差値42から62へ。地方の公立高校から、東大A判定へ。これが「プレミアムな自分」なのかもしれない。
ただし、繰り返すが、このサービスは決して安くない。そして、向き不向きもある。だから、まずは無料体験で自分に合うか確かめることをおすすめする。
あの日、半信半疑で申し込んだ無料体験。それが私の人生を変えた。次はあなたの番かもしれない。