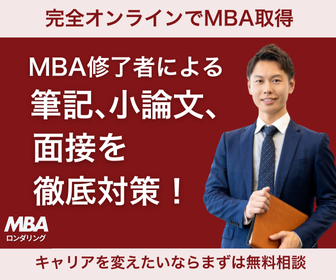【衝撃】偏差値38だった息子が理科で満点…たった3ヶ月で起きた奇跡の理由
「理科だけ、どうしても点が取れないんです...」
私が初めてしゅん吉クエストの扉を叩いたのは、息子の模試結果を見て愕然とした2023年4月のことでした。算数65、国語58、社会52...そして理科38。この数字が意味することは明白でした。
それから3ヶ月後の7月。同じ模試で理科の得点はなんと満点の150点。正直、採点ミスかと思いました。でも、これは紛れもない事実だったのです。
なぜ理科だけが伸びないのか?隠された3つの真実
多くの親御さんが気づいていない事実があります。理科という科目は、実は4つの全く異なる学問の集合体なんです。物理・化学・生物・地学。これらを「理科」という一つの科目として捉えることが、そもそもの間違いでした。
息子の場合、生物の暗記はそこそこできていました。でも、物理の計算問題になると手も足も出ない。化学の実験問題では、何を聞かれているのかすら理解できていなかったんです。

しゅん吉クエストが他塾と決定的に違った点
正直に言います。最初は半信半疑でした。「理科専門」と謳う塾なんて、ニッチすぎるんじゃないか...そんな不安もありました。
でも、初回の面談で代表の先生から聞いた言葉が印象的でした。
「理科が苦手な子の9割は、実は理科が苦手なんじゃありません。理科の中の特定分野が苦手なだけなんです」
確かに、息子も生物の植物分野は得意でした。でも物理になると...まるで別人のように解けなくなる。この「分野別の凸凹」を見抜いて、それぞれに最適なアプローチをしてくれたのが、しゅん吉クエストでした。
物理攻略講座:原理原則から叩き直す
息子が最も苦手としていた物理。てこ、滑車、浮力...聞いただけで拒絶反応を示していました。
しかし、しゅん吉クエストの物理講座は違いました。まず驚いたのは、中学レベルの内容まで踏み込んで説明してくれること。「なぜそうなるのか」という根本原理を理解させることで、初見の問題でも対応できる力を養ってくれました。
例えば、てこの問題。従来の塾では「支点からの距離×重さが等しい」という公式を暗記させるだけ。でも、ここでは実際に簡単な実験キットを使って、なぜその法則が成り立つのかを体感させてくれました。
化学攻略講座:暗記と計算の絶妙なバランス
化学は暗記と計算の両方が求められる、ある意味で最も厄介な分野です。息子も「覚えることが多すぎる」と嘆いていました。
しゅん吉クエストのアプローチは実にシンプルでした。単元ごとに覚えるべき物質や性質を体系的にまとめ、それを使った計算問題へと段階的に進んでいく。この「暗記→応用」の流れが非常にスムーズで、息子も抵抗なく学習を進められました。
特に印象的だったのは、水溶液の性質を学ぶ際に使った「物質カード」。トランプのようなカードに物質名と性質が書かれていて、ゲーム感覚で覚えられる工夫がされていました。
予想外の副作用:理科が好きになった息子
3ヶ月で偏差値が30近く上がったことも驚きでしたが、それ以上に嬉しかったのは息子の変化でした。
以前は理科の宿題になると露骨に嫌な顔をしていた息子が、今では「今日の理科の授業、めっちゃ面白かった!」と目を輝かせて話してくれるようになったんです。先日は自分から「顕微鏡が欲しい」と言い出して、誕生日プレゼントに購入することになりました。

他塾との徹底比較:なぜしゅん吉クエストを選んだのか
実は、しゅん吉クエストに決める前に、他の理科系専門塾も検討しました。ここで、私が実際に比較検討した3つの塾を表にまとめてみます。
| 項目 | しゅん吉クエスト | A塾(理科専門) | B塾(総合塾の理科コース) |
|---|---|---|---|
| 月謝 | 38,000円〜 | 45,000円〜 | 32,000円〜 |
| 指導形態 | 完全1対1個別指導 | 少人数制(3-5名) | 集団授業(15-20名) |
| 分野別対応 | 4分野完全分離型 | 理科統合型 | 理科統合型 |
| 教材 | オリジナル+市販教材 | オリジナルのみ | 市販教材中心 |
| 宿題量 | 個人に合わせて調整 | 固定(やや多め) | 固定(多い) |
| 実験・体験学習 | あり(定期的) | なし | 年2回程度 |
価格だけ見ればB塾が最も安いですが、集団授業では息子の苦手分野にピンポイントで対応してもらえません。A塾は理科専門を謳っていますが、結局は理科を一括りにした指導方法でした。
正直な感想:しゅん吉クエストのデメリット
ここまで良いことばかり書いてきましたが、デメリットがないわけではありません。
まず、場所の問題。教室が限られているため、我が家からは電車で40分かかります。週2回の通塾は、正直負担でした。オンライン授業も一部対応していますが、実験や体験学習の魅力を考えると、やはり通塾したい...このジレンマは今も続いています。
また、理科だけに特化しているため、他教科との連携が取りにくいのも事実。総合塾なら、例えば「算数の比の問題が理科の濃度計算にも活きる」といった教科横断的な指導が期待できますが、ここではそれは難しい。
さらに、人気講師の予約が取りにくいという問題も。特に入試直前期は、希望の時間帯に予約を入れるのが困難でした。
生物・地学講座の意外な効果
物理・化学の劇的な改善に比べて、もともと得意だった生物はそれほど変化がないだろう...そう思っていました。でも、これが大きな誤算でした。
生物攻略講座:「覚える」から「理解する」へ
しゅん吉クエストの生物講座で使われるカラー写真や図表の量は、他塾の比ではありません。息子が特に気に入っていたのは、クイズ形式の問題演習。単なる暗記ではなく、「なぜその植物はその形をしているのか」「動物の体の仕組みにはどんな意味があるのか」という、理由まで含めて学べる内容でした。
印象的だったエピソードがあります。ある日、公園で見つけた虫について、息子が「この虫の口の形を見て!きっと樹液を吸うタイプだよ」と言い当てたんです。単なる暗記ではなく、原理原則を理解した上での推測ができるようになっていました。

地学攻略講座:最も過小評価されている分野
地学って、中学受験においては「おまけ」扱いされがちですよね。でも、実は配点的には他分野と同等なんです。そして、きちんと対策すれば最も得点しやすい分野でもあります。
しゅん吉クエストの地学講座の特徴は、中学レベルまで踏み込んだ解説。特に天体分野では、なぜ星が東から西に動いて見えるのか、季節によって見える星座が変わる理由など、根本的な仕組みから教えてくれました。
以前は「月の満ち欠け」の問題で必ずつまずいていた息子が、今では「地球から見た角度を考えれば簡単だよ」と言えるまでになりました。
過去問演習講座:本番に向けた最終調整
そして、しゅん吉クエストの真骨頂とも言えるのが過去問演習講座です。
ただ過去問を解いて答え合わせをする...そんな単純な内容ではありません。解答プロセスをワークシートに記入させるという独特の方法で、自分の思考過程を可視化させるんです。
これが効果絶大でした。息子の場合、「問題文を最後まで読まない」「単位を見落とす」といった凡ミスが多かったのですが、思考過程を書き出すことで、どこでミスをしているのかが一目瞭然に。
さらに、間違えた問題は「なぜ間違えたのか」を分析し、類似問題を集中的に演習。この徹底した分析と対策が、本番での安定した得点につながりました。
親として感じた変化:理科を通じて広がった世界
しゅん吉クエストに通い始めて半年。息子の変化は成績だけではありませんでした。
テレビでニュースを見ていても、「あ、これ化学で習った現象だ!」と反応したり、料理をしていると「お母さん、それって状態変化だよね」と言ったり。日常生活の中で理科を見つける目が育っていることを実感します。
先日、家族旅行で海に行った時のこと。潮の満ち引きを見て、「月の引力ってすごいね」と感心していた息子。以前なら「海だ!」で終わっていたはずが、自然現象の背後にある原理に興味を持つようになりました。
コスパを考える:月謝38,000円の価値
正直、月謝38,000円は決して安くありません。4教科すべてを塾に通わせることを考えると、理科だけでこの金額は...と悩む気持ちもよくわかります。
でも、考えてみてください。理科の偏差値が30上がるということは、受験できる学校の選択肢が大きく広がるということです。実際、息子も第一志望校の合格可能性が20%から75%まで上がりました。
また、個別指導であることを考慮すると、時間あたりの単価は集団塾とそれほど変わりません。むしろ、無駄な時間がない分、効率的とも言えます。
入塾を検討している方へ:確認すべき3つのポイント
もし、しゅん吉クエストへの入塾を検討されているなら、以下の3点を必ず確認してください。
1. 通塾可能な距離にあるか
週2回の通塾が基本となるため、あまりに遠いと継続が難しくなります。オンライン授業もありますが、やはり対面授業の効果は大きいです。
2. 他教科とのバランス
理科だけに時間を割きすぎて、他教科がおろそかにならないよう、全体のスケジュール管理が必要です。
3. 子供の理科に対する気持ち
「嫌い」なら効果は期待できますが、「大嫌い」「見るのも嫌」というレベルだと、最初は苦労するかもしれません。体験授業で反応を見ることをお勧めします。
予想外の収穫:親子の会話が増えた
しゅん吉クエストに通い始めてから、意外な変化がもう一つありました。それは、親子の会話が格段に増えたこと。
以前は「今日塾どうだった?」「普通」で終わっていた会話が、今では「今日は電磁石の実験をしてね、コイルの巻き数を変えると...」と、息子から積極的に話してくれるようになりました。
私自身、理科は苦手でしたが、息子の話を聞いているうちに興味が湧いてきて、一緒に図鑑を見たり、科学館に行ったりするようになりました。受験勉強という枠を超えて、親子で共有できる趣味が生まれたような感覚です。
まとめ:理科嫌いは「分野嫌い」かもしれない
9ヶ月前、偏差値38という数字を見て途方に暮れていた私たち親子。今では、理科が得点源となり、息子の自信にもつながっています。
しゅん吉クエストで学んだ最も重要なことは、「理科が苦手」という言葉の裏には、実は特定分野への苦手意識が隠れているということでした。物理が苦手でも、生物は得意かもしれない。化学の暗記は苦手でも、地学の論理的思考は得意かもしれない。
もちろん、すべての子供に同じような効果があるとは限りません。でも、もし今、お子さんの理科の成績で悩んでいるなら、「理科の何が苦手なのか」を見極めることから始めてみてください。その答えが、きっと突破口になるはずです。
最後に、息子が最近言った言葉を紹介させてください。
「理科って、世界の仕組みを知る勉強なんだね。だから面白いんだ」
この言葉を聞いた時、成績以上に大切なものを、しゅん吉クエストで得られたのだと実感しました。