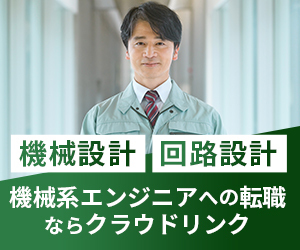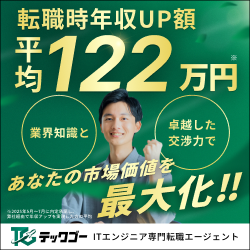月額手数料0円の衝撃...私がビルドサロンで年間120万円節約できた理由と落とし穴
「月額売上の20%が手数料で消えていく...」これが私がオンラインサロン運営で直面した現実でした。月商600万円の売上から、毎月120万円が手数料として消えていくのを見て、何か別の方法はないかと探し始めたのが2年前。
そんな時に出会ったのが、東京都新宿区にある株式会社ビルドサロンという会社でした。「買い切り型でランニングコスト0円」という言葉に半信半疑だった私が、実際に導入してみて分かったことをお伝えします。
ビルドサロンとは?オンラインサロン制作の専門企業
ビルドサロンは、法人向けにオンラインサロンの制作を専門に行っている企業です。最大の特徴は、完全買い切り型でサービスを提供している点。つまり、一度制作費を支払えば、その後の月額費用や売上手数料は一切かからないという仕組みです。
実は私も最初は「本当にそんなことが可能なの?」と疑っていました。他社のオンラインサロンプラットフォームは、どこも月額費用や売上手数料を取るビジネスモデルだったからです。
なぜランニングコスト0円が実現できるのか
ビルドサロンが提供するのは、プラットフォームではなく「あなた専用のウェブサイト」です。WordPressなどのCMSを使って、完全にオリジナルの会員制サイトを構築し、それをお客様に納品するという形式を取っています。
つまり、自分でウェブサイトを所有することになるため、誰かに手数料を払う必要がないというわけです。必要なのはサーバー代(月額数千円程度)とドメイン代(年額数千円)のみ。
実際に使ってみて分かった本音レビュー
私がビルドサロンでオンラインサロンを制作してもらってから、約1年半が経過しました。その間の経験を踏まえて、良かった点と注意すべき点を正直にお伝えします。
驚いた点:想像以上の機能充実度
正直、買い切り型ということで機能面では期待していませんでした。しかし実際に納品されたサイトを見て驚いたのは、大手プラットフォームに引けを取らない機能の充実度でした。
- 会員登録・ログイン機能
- 月額・年額プランの設定
- コンテンツの段階的公開
- 会員限定の掲示板機能
- 動画・音声コンテンツの配信
- 会員へのメール一斉送信
- 決済システムの統合(Stripe、PayPal対応)
特に便利だったのは、会員の行動履歴を細かく分析できる機能です。どのコンテンツが人気なのか、会員の継続率はどうか、といったデータを自由に取得できるのは、自社サイトならではのメリットでした。
予想外だった点:初期設定の複雑さ
一方で、想定外だったのは初期設定の複雑さです。プラットフォーム型のサービスなら、アカウントを作ってすぐに使い始められますが、ビルドサロンの場合は自分でサーバーを契約したり、ドメインを取得したりする必要があります。
私の場合、IT知識がほとんどなかったので、最初の1週間はマニュアルとにらめっこでした。ただ、LINEでのサポートが充実していたので、分からないことはすぐに質問できました。返信も早く、画像付きで丁寧に説明してもらえたのは助かりました。
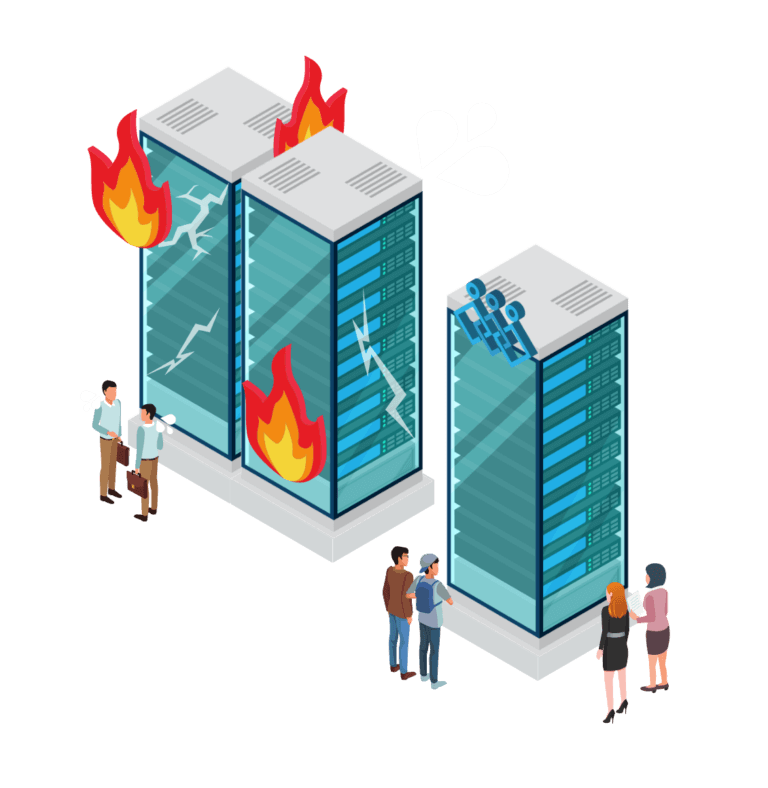
他社サービスとの詳細比較
実際にビルドサロンを選ぶ前に、私は主要なオンラインサロンプラットフォームと比較検討しました。その時の比較表を共有します。
| 項目 | ビルドサロン | DMMオンラインサロン | CAMPFIREコミュニティ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 60万円〜 | 0円 | 0円 |
| 月額費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 売上手数料 | 0% | 20% | 10% |
| カスタマイズ性 | ◎(完全自由) | △(制限あり) | ○(ある程度可能) |
| データ所有権 | 完全に自社 | プラットフォーム側 | プラットフォーム側 |
| サービス終了リスク | なし | あり | あり |
| 集客サポート | ×(自力) | ◎(プラットフォーム内露出) | ○(一部サポート) |
この比較表を見ると分かるように、ビルドサロンは初期投資は必要だが、長期的に見ると圧倒的にコストパフォーマンスが良いということが分かります。
損益分岐点の計算
私の場合、月商600万円で他社プラットフォームなら20%の手数料(120万円)がかかっていました。ビルドサロンの初期費用が約100万円だったので、たった1ヶ月で元が取れる計算になります。
もちろん、売上規模によってこの計算は変わってきます。月商50万円程度なら、手数料は月10万円。この場合、10ヶ月で初期投資を回収できることになります。
ビルドサロンのメリット・デメリット
1年半使ってみて感じた、ビルドサロンの良い点と改善してほしい点をまとめました。
メリット
- 完全なコスト削減:売上が増えても手数料が増えない安心感
- 自由度の高さ:デザインも機能も思い通りにカスタマイズ可能
- データの完全所有:会員データを自由に活用できる
- 永続性:サービス終了の心配がない
- SEO対策:独自ドメインで検索順位も上げやすい
デメリット
- 初期投資が必要:最低でも60万円からという価格設定
- 技術的な知識が必要:サーバー管理など最低限の知識は必要
- 集客は自力:プラットフォームからの流入は期待できない
- アップデートは有料:新機能追加には追加費用がかかる場合も

どんな人にビルドサロンは向いているか
実際に使ってみて、ビルドサロンが向いている人と向いていない人がはっきりと分かりました。
向いている人
- 月商100万円以上のオンラインサロンを運営している
- 長期的な事業として本気で取り組みたい
- 会員データを活用したマーケティングをしたい
- 独自のブランディングを重視する
- 手数料に悩まされている
向いていない人
- まずは試験的に始めたい
- 初期投資を抑えたい
- IT関連の作業が極端に苦手
- プラットフォームの集客力に期待している
- 月商50万円未満の小規模運営
特に重要なのは、「本気度」と「規模」です。趣味程度で始めるなら、正直他社のプラットフォームの方が手軽です。しかし、事業として本格的に取り組むなら、ビルドサロンの方が圧倒的に有利になります。
導入前に知っておくべき注意点
ビルドサロンを導入する前に、私が「もっと早く知っておけば良かった」と思った点がいくつかあります。
1. サーバー選びは慎重に
ビルドサロンから推奨されるサーバーはありますが、会員数が増えることを想定して、最初から余裕のあるプランを選ぶべきです。私は最初ケチって安いプランにしたら、会員が500人を超えた頃からサイトが重くなり、プラン変更で苦労しました。
2. バックアップ体制の構築
自社でサイトを持つということは、データのバックアップも自己責任ということです。自動バックアップの設定は必須。私は月に1回、手動でもバックアップを取るようにしています。
3. セキュリティ対策
会員の個人情報を扱うので、セキュリティは本当に重要です。ビルドサロンはISO27001を取得しているので基本的な対策は施されていますが、運営側でもSSL証明書の更新や、定期的なパスワード変更など、基本的な対策は必要です。
実際の導入フローと期間
私が実際に経験した導入フローを時系列で紹介します。
- 初回相談(1日目):オンラインで要望をヒアリング
- 見積もり提示(3日目):詳細な見積もりと機能一覧
- 契約・着手金支払い(5日目):契約書締結と50%の着手金
- 要件定義(7-10日目):詳細な機能やデザインの打ち合わせ
- デザイン確認(14日目):トップページのデザイン案確認
- 開発期間(15-25日目):実際の開発作業
- テスト環境での確認(26-28日目):動作確認と修正
- 本番環境への移行(30日目):正式リリース
- 運用開始(31日目〜):実際の運営スタート
私の場合は約1ヶ月で完成しましたが、カスタマイズの内容によっては2-3ヶ月かかることもあるそうです。
1年半運営してみた成果
最後に、ビルドサロンでオンラインサロンを運営して1年半の成果を共有します。
- 会員数:350人→1,200人(約3.4倍)
- 月商:600万円→950万円(約1.6倍)
- 利益率:60%→85%(手数料がなくなったため)
- 継続率:月次85%→92%(カスタマイズで使いやすさ向上)
特に大きかったのは利益率の改善です。売上が1.6倍になっただけでなく、手数料がなくなったことで、実際の利益は2倍以上になりました。
また、自由にカスタマイズできることで、会員の要望に素早く対応できるようになり、結果として継続率も向上しました。「こんな機能が欲しい」という声に、外注で対応できるのは大きなメリットです。
まとめ:ビルドサロンは「投資」として考えるべき
ビルドサロンは決して安い買い物ではありません。しかし、長期的な視点で見れば、確実に回収できる投資だと私は考えています。
ただし、それは「本気でオンラインサロン事業に取り組む」という前提があってこそ。試験的に始めたい、とりあえず様子を見たい、という方には向いていません。
もしあなたが、すでにある程度の規模でオンラインサロンを運営していて、手数料に悩んでいるなら。あるいは、これから本格的にオンラインサロン事業を立ち上げたいと考えているなら。ビルドサロンは検討する価値があると思います。
私自身、最初は「60万円は高い...」と思いました。でも今では「もっと早く導入すれば良かった」と思っています。毎月の手数料を考えれば、この初期投資は決して高くありません。
ビルドサロンが合うかどうかは、あなたの事業規模と本気度次第。まずは相談だけでもしてみることをお勧めします。私も最初の相談で、かなり具体的なアドバイスをもらえました。